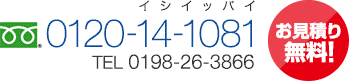以前にも紹介をさせていただきました石のセガワのサービス「すまいる・くらぶ」。すまいる・くらぶは、日常の“お困りごと解決”のお手伝いをさせていただいております。
今回は、今までご依頼いただいた中から一つの事例をご紹介させていただきます。
ご依頼いただいたのは、70代の女性の方でした。
ご実家のご家族がお亡くなりになり、お墓じまいのご依頼を受け工事をさせていただきました。作業完了後に弊社の「すまいるくらぶ」のパンフレットをご覧になって再度、ご連絡をいただきました。
ご実家にもう住む方がいないので片づけをしたいと考えているというご相談でした。
まずは、協力会社である専門業社と一緒に現状を確認させていただき、お見積りをさせていただきました。お客様は、ご兄弟とご相談され、その後正式にご依頼をいただきました。
仏壇や神棚、人形については、石のセガワでお引き取りさせていただき供養後に処分させていただきました。その後、敷地内にある住居用の家の他に作業小屋、物置小屋、庭などにあったすべての物を搬出させていただきました。


お客様は、片づけを考えていたもののどこに頼んでいいかわからずにいたそうです。
お墓のことはもちろんですが、供養に関すること、遺品供養や遺品整理、お住まいの片づけやお掃除などのお困りごとがございましたら是非、石のセガワへご相談ください。
すまいる・くらぶの詳しいサービス内容はコチラ